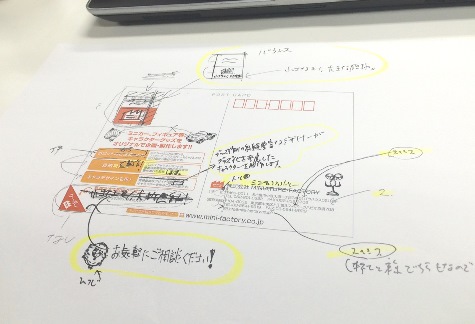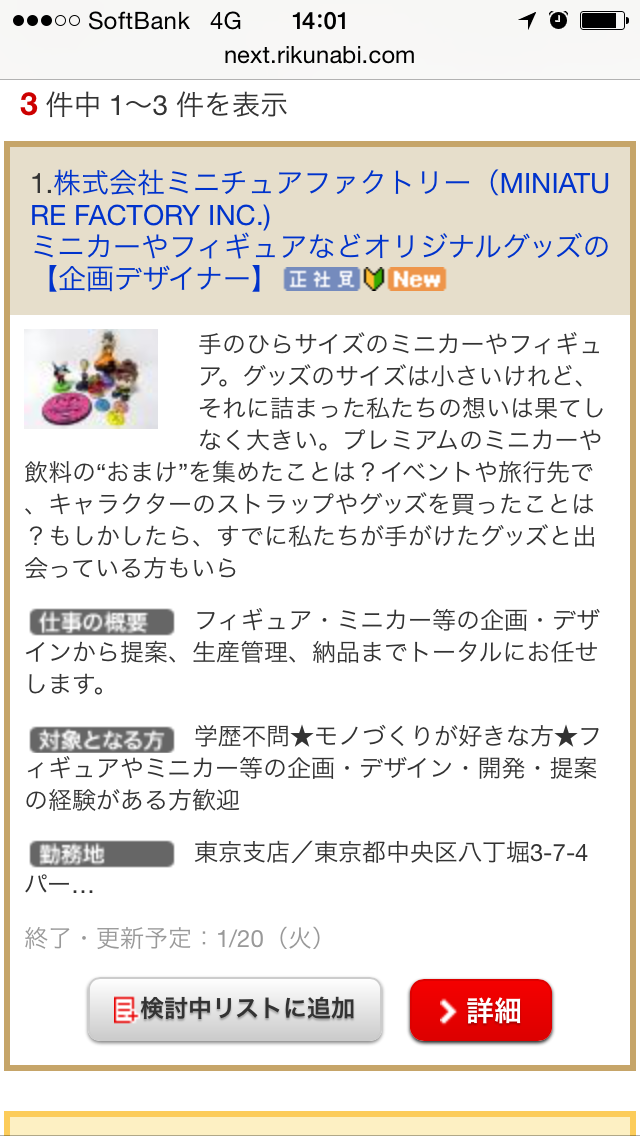さて、昨日はプロジェクトマネジメント手法であるCCPMについて書きました。
CCPMとは、クリティカルチェーンプロジェクトマネジメントの略です。
こう書くと、初めて聞く人には難しく聞こえてしまうかもしれませんが、よく内容を知れば、実態は極めて常識的で普通の管理方法です。
ただし常識といっても、従来の常識とはいささか異なることも多いのですが。
たとえば、下記の常識について考えてみてください。
・プロジェクトをなるべく早く開始した方が早く終わる。
これって正しいですか?
一見、正しいですよね?
では、こちらはどうですか?
・無駄のない緻密なスケジュールを組む。
これもどうですか?
正しく聞こえますよね。
では、これは?
・プロジェクトを計画通り進むように管理する。
これも正しいと思いますか?
実はこれらはほとんどの場合、全体の状況を考えると正しくありません。
とりあえず今回は、
・プロジェクトをなるべく早く開始した方が早く終わる。
という常識を取り上げて考えてみましょう。
もし、その組織内にひとつのプロジェクトしかなく、各メンバーの業務が直線的につながっているならばこの常識は正しいでしょう。
でも実際の仕事では、各スタッフが複数のプロジェクトを掛け持ちでおこなっていることが多いですね。
それで、どっちを優先するかわからない時もあったりしませんか?
その優先順位とは組織全体にとっての正しい優先順位で決まっていますか?
マネージャー間の力関係で決まっていたりしませんか?
もし誰かが間違った優先順位で選んだプロジェクトに従事していたら、その分のリソース(人)はその間は使えませんから
全体にとって重要な工程が停滞することになってしまいます。
複数のプロジェクトを抱える環境(マルチプロジェクト環境)では、どのプロジェクトも先を争って開始しようとし、リソースの奪い合いが起きることが多く、その結果それぞれのプロジェクトはスムーズに進まなくなってしまいます。
これを防ぐためには、組織全体にとって誰もが納得できる正しい優先順位を決めることによりリソースの奪い合いを避けることが必要です。そのような判断基準はあるのでしょうか?
常識は一見正しそうに思えることでも、実は深く考えると正しくないことがあります。
それをよく理解して挑む必要があるのです。
詳しくはまた書きますね。
Takuro